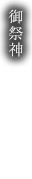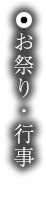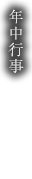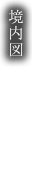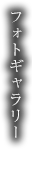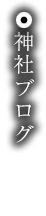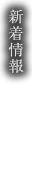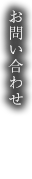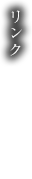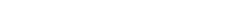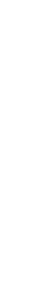八幡神社絵馬の旅 その⑥ 玉井勝流稚継 筆「源義光 足柄山ニテ笙ノ秘曲ヲ豊原時秋二授クルノ事」の図
2015年2月22日 8:15 PM
さて、6回目となりました八幡神社絵馬の旅。今回ご紹介するのは、「源義光 足柄山ニテ笙ノ秘曲ヲ豊原時秋二授クルノ事」の図です。数十年前は拝殿の絵馬の裏に隠れるように掲げられておりましたが、倒れる危険ありとのことで取り外し、保管しておりました。
この絵馬は、13世紀前半に編さんされた「古今著聞集」に書かれた説話を絵馬に描いたもので、慶応3年(1867)に奉納されました。恐らく、公開するのははじめてではないでしょうか。
この絵馬に描かれた源義光(右側の赤い装束)は平安時代中期の武将で、射術に優れ、新羅明神の社前で元服したころから“新羅三郎”とも呼ばれ、雅楽の笙(しょう)の名人として名を馳せました。この絵馬でも笙を吹いているのがわかります。
義光の左側、月明かりの下で笙の音を聴いているのは豊原時秋 (とよはらのときあき)。豊原家は宮中の笙(しょう)の楽家で、時秋は若当主。時秋の亡き父、時元は笙の名人であり、時元の一番弟子が源義光でした。
さて、この絵馬にはどんな物語が描かれているのでしょうか。「古今著聞集」の話を要約すると・・・。
時は永保3年(1083)の後三年の役の頃。兄である源義家の加勢のため奥州にむかった義光のもとに、後ろから馬を飛ばして追いかけてくる若者がいます。それが豊原時秋でした。時秋を幼い頃からよく知っていた義光は大変驚き「これは一体どういうことか。何をしにこられたのか」と尋ねたところ、時秋はただ「お供させてください」と申し出ます。義光は、違和感を感じつつ、「連れて行ってあげたいのはやまやまですが、今回ばかりはなりません」と断ります。それもそのはず、今回の加勢は朝廷からの許しが出ず、自らの職を辞して馳せ参じるもの。若当主たる時秋を巻き込むわけにはいきません。
しかし、何度諭しても時秋は強情についてきます。そしてとうとうそのまま、現在の神奈川県にある足柄山にさしかかりました。この山の関所は厳しく、関所破りともなれば、もう京都に引き返すことは出来ません。義光は 時秋を 呼んでこう言いました。「ここまでついてこられたということはその志は浅からぬものがあったでしょう。しかし、貴方はやはりここから帰りなさい」。それで も、黙って時秋は帰ろうとしません。
楽家の若当主の助太刀という奇妙な申し出と時秋の真剣な表情を見ているうちに、義光はふとあることに気がつきます。
やおら義光は、周囲の人を遠ざけて時秋を連れて足柄山の山頂に行き、盾を2枚敷いて1枚に座り、もう1枚には時秋を座らせ言いました。
「笙を持っておられますね」
「はい」
時秋はそう言うと懐から笙を取りだし ました。義家は腰の矢入れから一枚の紙を取り出しました。「これは、あ なたの父上が書かれた大食調入調(たいしきちょうにっちょう)の譜です。さあ、お教えいたしましょう」。こ の秘曲は昔、義光が時元から伝授を受けたものでした。時元が亡くなったとき時秋はまだ子供でこの曲を教わっていませんでした。このことを知っていた時秋 は、豊原家の秘曲が絶えることを危惧し、この曲の伝授を受けるためにやって来たのでした。しかし、命を賭して奥州に向かうさ最中の義光に「秘曲を伝授して欲しい」などとは言えな かったのでしょう。義光が秘曲のことに気づいてくれない場合は、奥州で討ち死にする覚悟で付いて来たのだといわれています。そして月明かりの下、義光は時秋に入調の秘曲を授けたのでした。義光は、この若者の心がけに感心すると共に、笙の道に専念するように諭し、時秋を都に返しました。その後時秋は笙の第一人者として活躍し、雅楽頭(うたのかみ)、楽所別当となったといわれています。
改めて見てみると、命を賭した関所破りを前に、この秘曲を伝えることができることに安堵し、清々しく面持ちで笙を吹く源義光と、神妙な顔つきで耳を傾ける時秋の表情のコントラストが絶妙です。特に時秋の何とも言いがたい表情に惹きつけられますね。
話が長くなりましたが、この絵馬を描いたのは、新谷の玉井勝流稚継(閑林斎、洋々斎)です。稚継は、若宮養徳の嗣子若宮晴徳の門人として活躍しました。晩年は大洲領であった砥部で砥部焼の絵付けをしていたとか。
そして絵馬の裏には、当時の奉納者の方々の名が記されています。ご覧になった方で、御子孫や、この方々を知っておられる方がいらっしゃいましたら神社までご一報いただければ幸いです。
家の伝統を絶やさず守ろうとする若者の想い、しかしそれを自らは言い出さぬ奥ゆかしさ、懐に忍ばせた笙。そしてはからずとも肌身離さず亡き父の譜面を持ち続けた義光。この説話からは多くのことを感じ、学ぶことができます。 最近は、こうした昔の説話を聞くことがめっきりなくなりました。特に子供達には、こうした説話を通して日本の心を感じてもらいたいものです。